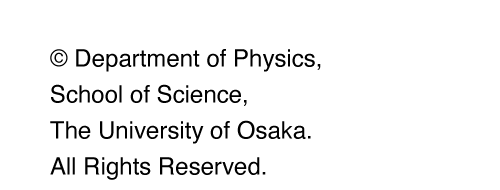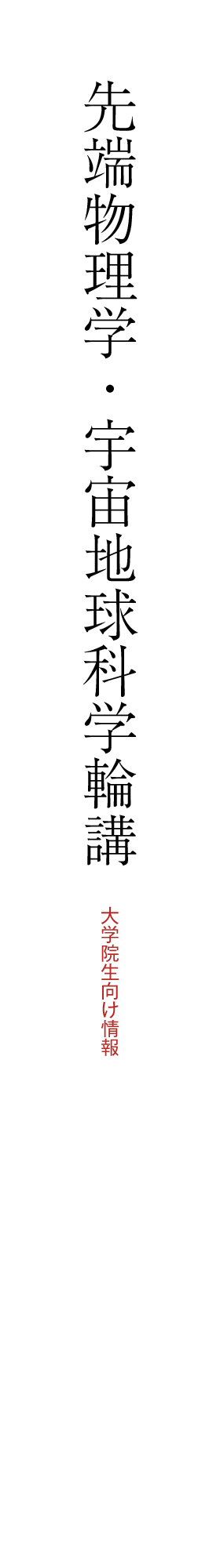
2016(H28)年度
先端物理学・宇宙地球科学輪講
●日時
2学期 金曜日4時限(14:40〜16:10)
●場所
理学部D501大講義室
●出席
毎回、回覧される出席表に自筆で署名してください
レポートについて
●提出回数
下の日程表に示す2〜3回の講義の組につき1つのレポートを提出する。提出するレポートの数は合計5つ。
●内容
興味や関心を持った講義について、その内容をまとめる。さらに、内容に関連してさらに自分で調べたこと、あるいは疑問に思ったことを書いてもよい。
●形式
A4紙で2〜4枚程度。1枚は不可。
1ページ目の初めに
・講師名、表題
(改行して)
・学科、学年、学籍番号、氏名
を明記し、続けて同じページからレポート内容を書いてください。
●提出先
理学部H棟4階物理事務室(H408)の扉の横の「鍵返却・レポート提出用メールボックス」
講義日程とレポート提出期限
レポート 提出期間:2016/10/24〜10/28
詳細
2016.10.7
ガイダンス
●谷口年史(宇宙地球科学専攻)
2016.10.14
人工量子系の物理学
●小林研介(物理学専攻)
携帯電話やパソコンなど、私たちの身のまわりには、高度なエレクトロニクス技術を駆使した、たくさんの電子機器があります。エレクトロニクスとは「電子をあやつる」技術のことです。
量子力学とエレクトロニクスの歴史を振り返ってみると、私たち人類が、どのように電子を制御する技術を身につけてきたのか、よく分かります。さらに、近年、ナノテクノロジーの発展にともなって、極小の電子回路を用いた新しいエレクトロニクス「人工量子系」の研究が進んでいます。例えば、電子を一個ずつ操る技術や、電子を波として扱う技術、量子コンピュータの基本素子などが開発されています。
私たちはどこまで電子を制御できるのでしょうか?
私たちはどこまで量子力学を制御できるのでしょうか?
今回の講義では、量子力学とエレクトロニクスの歴史、ナノテクノロジー、そして最新の研究成果までをご紹介します。
ポスター
2016.10.21
ミューオンで探る素粒子の世界
●青木正治(物理学専攻)
ミューオンは電子型粒子(荷電レプトン)の第2世代にあたる素粒子です。ミューオンは70年以上昔に発見された「古い」素粒子ですが、今このミューオンを使ったさまざまな「新しい」素粒子実験が世界中で計画されています。
この講演では、素粒子物理学の基礎とミューオンの魅力、ミューオンを用いた素粒子実験の紹介をします。
ポスター
レポート 提出期間:2016/11/14〜11/18
詳細
2016.10.28
第二の地球と生命を探す
●芝井 広(宇宙地球科学専攻)
太陽系外の惑星がすでに2000個以上、発見されている。これらの惑星のほとんどは、太陽系の惑星と似ても似つかぬものであり、従来の標準的な太陽系形成論では、その形成過程が説明できない例が多い。本講義では、発見が相次ぐ太陽系外惑星研究の最前線を解説するとともに、第二の地球と生命の探索の研究方向に触れる。
ポスター
2016.11.11
電子正孔系の物理
●浅野建一(物理学専攻)
強い光を照射した半導体中では、同数の電子と正孔が多数共存する系(電子-正孔系)が実現される。この系が示す多彩な振る舞いについて紹介する。
ポスター
レポート 提出期間:2016/12/5〜12/9
詳細
2016.11.18
大型レーザーで探る宇宙:レーザー宇宙物理
●坂和洋一(レーザーエネルギー学研究センター)
近年、世界各国の大型レーザーを用いて、宇宙で観測されている物理現象を実験室で解明しようという、「レーザー宇宙物理」の研究が進められています。
我々は、超新星残骸や地球磁気圏で観測されている、粒子間のクーロン衝突がほとんど無視できる無衝突プラズマ中での衝撃波、無衝突衝撃波に関する実験を中心に行っています。
講演では、このようなレーザー実験の詳細を紹介をします。
ポスター
2016.11.25
「極限強磁場の科学」
●鳴海康雄(先端強磁場科学研究センター)
磁場は、電子が持つスピンやその軌道運動に直接作用する、科学研究に不可欠なユニークかつ制御性の高い外場です。我々物性研究者は、天文学における宇宙望遠鏡の高性能化と同様に、磁場領域の拡大によって新しい物性現象を発見してきました。
当研究室では、1万アンペアを越える大電流を生み出す国内最大の10メガジュールコンデンサー電源を用いて、世界でも数少ない50テスラを越える超強磁場を発生し、その磁場中に置かれた物質が示す新奇な現象を探索しています。
この講義では、最新の強磁場発生技術と極限強磁場下で現れる新奇物性の学習を通して、「磁場とは何か」について考えます。
ポスター
2016.12.2
この世のすべてを記述する数式について
●橋本幸士(物理学専攻)
この世のすべてを記述する数式について
ポスター
レポート 提出期間:2017/1/10〜1/13
詳細
2016.12.9
自発的対称性の破れと磁性・超伝導・超流動
●青山和司(宇宙地球科学専攻)
「More is different」 モノの構成要素の数が増えると、その性質も複雑なものとなる。原子⇒モノ⇒地球⇒宇宙とスケールが大きくなるにつれ構成要素の数も著しく増大するため、その性質を知るには様々な切り口が必要となる。
本講演では、多体の協力現象の典型例として、磁性・超伝導・超流動を取り上げ、それらの類似性や最近の話題を紹介する。
ポスター
2016.12.16
大型レーザーで創る多様で魅力的な極限実験室
●藤岡慎介(レーザーエネルギー学研究センター)
大阪大学には国内最大のレーザー装置があるのをご存知でしょうか?吹田キャンパスにあるレーザーエネルギー学研究センターには、激光XII号レーザーとLFEXレーザーという、特徴の異なる二つのレーザーがあります。それぞれキロ・ジュールのエネルギーを持ちます。
これはちっぽけなエネルギーですが、レーザーの特徴である「集光性」「短パルス性」を利用することで、エネルギーを空間・時間的に集中し、エネルギー密度の高い状態を作りだすことが出来ます。 この「高エネルギ密度状態」を利用することで、数千万度の温度、数ペタ・パスカルの圧力、数キロテスラの磁場等々の、地上ではなかなか存在しない極限状態を作り出します。
本輪講では、レーザーで創り出す極限状態を利用した研究を紹介しながら、皆さんの柔らかい頭から発想される新しい実験の可能性について意見交換したいと思います。
ポスター
2017.1.6
宇宙の歴史
●藤田 裕(宇宙地球科学専攻)
宇宙が誕生してから約140億年たちます。極限の高密度状態からはじまった宇宙は、最初一様で単純なものでした。やがて膨張する宇宙の中で多種多様な天体が生まれ、現在のような多彩な宇宙になりました。そのような宇宙の歴史について最新の研究成果を交えてお話します。
ポスター
レポート 提出期間:2017/2/6〜2/10
詳細
2017.1.20
新物質の物理学−面白くて役に立つ物質の設計
●酒井英明(物理学専攻)
私たちは、身の回りにある物質をどこまで理解できているでしょうか。金属はなぜピカピカ光り電気を流すのか?温度を下げるとなぜその抵抗がゼロになるのか?鉄はなぜ磁石にくっつき、鉛筆の芯は磁石の上に浮くのか?実はこのような多種多様な性質は、すべて電子が担っています。電子は、電荷と自転運動(スピン)のたった2つの属性しか持ちません。しかし、物質の中では約1023個もの電子が量子力学に従い、互いに影響を及ぼし合っています。このため、個々の運動方程式からは予想もつかない、複雑な集団運動(創発現象)が生み出されます。私たちが普段当たり前と思って恩恵を受けている物質の性質のほとんどは、このような電子の創発現象の一端です。
物性物理学では、このような変幻自在の電子複雑系を相手とするため、新物質はしばしば重要な役割を果たします。従来は不可能とされてきた現象も、新物質において突然見つかることもあるからです。もちろん闇雲に探索するわけではなく、最新の理論計算や自分の直観をもとに、頭の中で物質を設計します。しかし実際に作れるとは限りません。そこで、時には超高圧や高真空、ソフトケミストリなど様々な化学的手法を駆使して、世界初の合成に挑みます。本講演では、物性物理学の基本とその奥深さを概説した後、講演者の研究を含む最先端の面白くて役に立つ物質の物理について紹介します。
ポスター
2017.1.27
相対論的重イオン衝突実験とQuark-Gluon Plasmaの物理
●赤松幸尚(物理学専攻)
宇宙誕生直後は、現在とは異なり超高温であったと考えられています。相対論的重イオン衝突実験は、この超高温物質を地上で作り出す実験です。ほぼ光速まで加速した原子核を正面衝突させると、約2兆度の超高温物質が約10-23秒間だけ存在します。この超高温物質はQuark-Gluon Plasma(QGP)と呼ばれ、宇宙誕生の約10-5秒後に宇宙を満たしていました。
談話会では、QGPとは何か?いかにしてQGPの物性に実験的に迫るか?、について解説します。その上でQGPの粘性やクォーコニウム抑制などの最近のトピックについても触れます。
ポスター
2017.2.3
物理と化学を駆使して活断層の動きを探る
●廣野哲朗(宇宙地球科学専攻)
先月17日で阪神淡路大震災発生から22年が経過しました。その間、東日本大震災や長野地震など多くの地震被害が発生しております。また、近い将来に
大阪平野での内陸型地震や東海-東南海-南海地震の発生が器具されています。
このような状況の中、現在、どのような地震研究・減災対応が進められているのか、その最先端を紹介しつつ、物理と化学を駆使して活断層の動きを探る研究の意義を説明します。
ポスター
輪講世話人
●谷口年史 F225, ttani あっと ess どっと sci.osaka-u.ac.jp
●(TA) 中西俊五
過去の先端物理学・宇宙地球科学輪講HP
2015年度