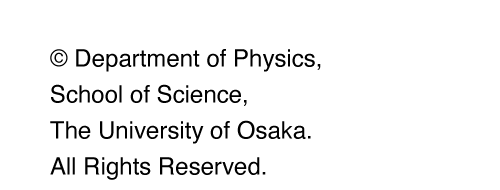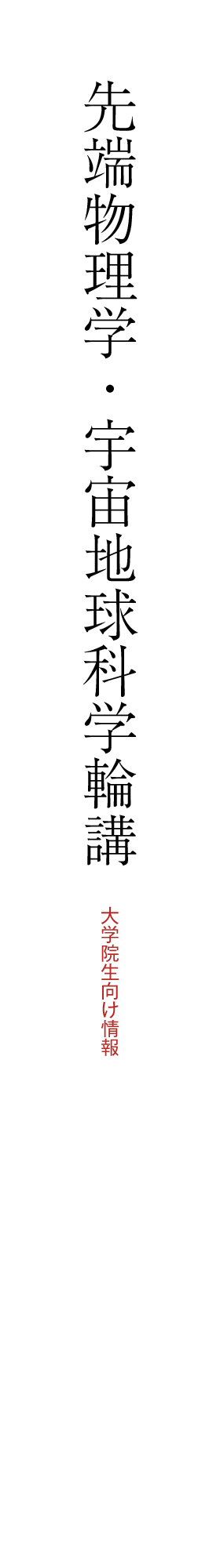
2019(R1)年度
先端物理学・宇宙地球科学輪講
●日時
秋・冬学期 金曜日4時限(14:40〜16:10)
●場所
理学部D501大講義室
●出席・レポート
毎回、授業中にミニレポートを書いて提出してください。
講義日程
第1回
2019.10.4
ガイダンス
●横田 勝一郎(宇宙地球科学専攻)
第2回
詳細
2019.10.11
ただし摩擦はあるものとする
●波多野 恭弘(宇宙地球科学専攻)
物理学は、摩擦や抵抗などを無視して「理想化」することで美しい法則を見出してきました。では逆に、摩擦や抵抗に注目してそれを理想化することで何か美しい法則が見つかるでしょうか?ようこそ、非平衡統計力学の世界へ・・・。
ポスター
第3回
詳細
2019.10.18
量子力学とエレクトロニクス 過去・現在・未来
●小林 研介(物理学専攻)
量子力学とエレクトロニクスの歴史を振り返ってみると、我々人類が、どのように電子を制御する技術を身につけてきたのか、よく分かる。現代のエレクトロニクスはどのように発展してきたのだろうか。量子力学はどのような役割を果たしてきたのだろうか。さらに、近年、ナノテクノロジーの発展にともなって、極小の電子回路を用いた新しいエレクトロニクスの研究が進んでいる。例えば、電子を一個ずつ操る技術や、電子を波として扱う技術、量子コンピュータの基本素子などが開発されている。我々は、電子を、量子力学を、どこまで制御できるのだろうか。本講義では、量子力学とエレクトロニクスの歴史、ナノテクノロジー、そして最新の研究成果を紹介する。
ポスター
第4回
詳細
2019.10.25
X線衛星でブラックホール近辺を探る
●野田 博文(宇宙地球科学専攻)
今年の春、史上初めてブラックホールを撮像したというニュースが世界を驚かせた。
これに代表される通り、ブラックホール研究は今や天文学・宇宙物理学における
一大テーマとなっており、様々な波長の観測を駆使した研究が進められている。
中でもX線は、ブラックホール近傍の領域における強重力下での物質の状態や
相対論的効果の情報を含んでいると期待され、これらを捉えるために、最先端の
X線検出器を搭載した天文衛星の開発が進んでいる。本講義では、ブラックホール
観測の最新の成果とともに、X線観測による今後の展望を紹介する。
ポスター
第5回
詳細
2019.11.8
原子からニュートリノを引き出せるか
●田中 実(物理学専攻)
皆さんは,ニュートリノは原子核や素粒子のベータ崩壊にのみ関わる不思議 な粒子で,およそ通常物質とは関係ないと思っておられるかもしれない.しかし,ベータ崩壊のみにニュートリノが関わるわけではない.素粒子物理の基礎である相対論的場の量子論に従うと,ニュートリノと電子の相互作用は,原子内電子の束縛状態変化によるニュートリノ・反ニュートリノ対放出という予言を導く.私たちの主たる物理目標は,このニュートリノ対生成を確認すること,対生成を利用してニュートリノの未知の性質を解明する ことにある.
ポスター
第6回
詳細
2019.11.15
クォークとハドロンと、ときどき新奇なハドロン
●野海 博之(核物理研究センター)
身辺の物質を分解していくと、それ以上分割できない素粒子、クォークとレプトン、に突き当たります。宇宙が爆発的に誕生して膨張とともに冷えるときに、クォークはハドロンという粒子群を形成します。最も安定なハドロンの2つが陽子と中性子で、これらは原子核を成します。普段、クォークを実感することはありませんが、それには訳があります。クォークには強い力が働き、自身をハドロンに閉じ込めてしまいます。ハドロンが強い力を早々に封じ込めたので、宇宙は様々豊かな物質であふれることになったといえるかもしれません。そんなハドロンの内部はどうなっているのでしょうか。強い力の紡ぐ世界は複雑でこの問いに答えることは一筋縄ではいきません。イマドキは個性ある新奇なメンバーが続々と見つかり、ハドロンの多様な姿が明らかになってきました。最近の研究をいくつか紹介します。
ポスター
第7回
詳細
2019.11.22
「はやぶさ2」が明らかにした小惑星「リュウグウ」
●佐々木 晶(宇宙地球科学専攻)
小惑星探査は、はやぶさ、はやぶさ2という探査機により、日本が世界を牽引している分野である。 長径500mほどのS型小惑星イトカワからのサンプルリターンに成功した「はやぶさ」に続き、「はやぶさ2」が計画された。 「はやぶさ2」は、2014年12月に打ち上げられ、昨年6月に900mほどのC型小惑星リュウグウに到着した。 C型小惑星は、炭素質隕石の源と考えられていて、生命の材料となる有機物や水を含んでいると考えられる。
リュウグウの密度は、1190kg/m3で空隙率50%程度のラブルパイル(瓦礫の寄せ集め)天体である。 赤道付近の盛り上がりは過去の高速時点を反映している。含水鉱物の存在を示す、2.7ミクロンの吸収帯は確認されているがその濃度は高くない。 これまでにわかったリュウグウの姿を紹介する。
11月13日に「はやぶさ2」はリュウグウを離れ、帰途についた。来年末にリュウグウの岩石の破片が入ったとみられるカプセルを分離し、オーストラリアの砂漠地帯に落下させ、回収する計画である。
ポスター
第8回
詳細
2019.11.29
原子核物理学と量子色力学
●石井 理修(核物理研究センター)
原子核は複数の陽子と中性子の量子力学的複合体です。陽子や中性子を原子核内部にとどめる力は核力と呼ばれる力で、π中間子を始めとする様々な中間子を交換することによって生じる力と理解されています。現在においては、陽子や中性子や、それにそれらの間の力を媒介する中間子も、すべてクォークとクォークの間の力を媒介するグルーオンからできていることが知られています。これを量子色力学といいます。これは要するに、陽子や中性子、それに中間子だけでなく、原子核までも全てひっくるめて量子色力学で取り扱い可能ということです。本講義では、ハドロン物理も含めて原子核物理への量子色力学の利用(の可能性)を考えていきます。
ポスター
第9回
詳細
2019.12.6
氷天体内部のH2Oが作る世界
●近藤 忠(宇宙地球科学専攻)
よく地球は水の惑星と言われますが、近年の様々な探査機による観測からは、太陽から遠く離れた氷の天体の内部にも液体水が存在している可能性が示唆されています。H2Oは我々にとって最も身近で不可欠な物質である一方で、身の回りにある物質の中では、最も例外的な性質を多数持つ物質でもあります。本談話会では、我々が取り組んでいる、氷天体の表層や内部に存在する氷や塩類を含む海の、不思議な性質に関する研究について紹介します。
ポスター
第10回
詳細
2019.12.13
隕石から探る太陽系起源と進化
●河井 洋輔(宇宙地球科学専攻)
隕石、惑星やその前駆小天体の「かけら」である。太陽系の起源と進化を明らかにする上で、隕石に含まれる元素存在度や同位体比に着目する物質科学的な手法は非常に重要である。例えば、放射性同位体の同位体比からは、その隕石の母天体がいつ形成されたのかを知ることができる。
これらの情報を得るための分析技術の開発も研究を進めるために必要である。講演では我々が開発している同位体顕微鏡についても紹介する。
ポスター
第11回
詳細
2019.12.20
地底から探る宇宙の謎
●吉田 斉(物理学専攻)
宇宙は物質でできていて、なぜ反物質はないのか?
宇宙はどのように進化して現在の宇宙の姿になっているのか?
この宇宙の壮大な謎を解くカギを握っているのが、
まだわかっていないニュートリノの性質や
未発見の宇宙暗黒物質であるといわれています。
日本の神岡地下実験室で行われているニュートリノや暗黒物質探索に関する
最先端研究を取り上げながら、宇宙の謎に迫る研究を紹介する。
ポスター
第12回
詳細
2020.1.10
統計物理学と生命の進化
●菊池 誠(サイバーメディアセンター)
統計物理学はたくさんのものが集まった時の平均的な振る舞いを研究する分野です。普通は原子や分子が集まった物質を対象にしますが、実は統計物理学の応用範囲はそれに限られず、なんでもいいからとにかくたくさん集まれば研究対象になります。ボルツマンのエントロピーはエネルギー以外になんの制約もない時に巨視的状態の実現しやすさを表し、エネルギー保存の制約のもとでもっともありふれた状態が熱平衡状態として実現します。熱力学系でない場合、エントロピーは真の意味での実現しやすさに対応するとは限りませんが、仮にさまざまな状態が全くランダムに出現するとしたら何が起きるかを知ることができます。私たちはランダムに作ろうとすればとんでもなく珍しいはずのものが現実に存在することを知っています。生命です。生命は長い進化の過程を経て作りあげられた珍しいものです。私たちは、統計物理学の手法を用いて得られるエントロピー最大の分布と進化シミュレーションとを比較することによって、進化という現象の特性を明らかにする研究を進めています。もちろん、簡単な「おもちゃモデル」でしか話はできませんが、これは生命進化を研究するための新しい方向性となるでしょう。この講演では遺伝子制御ネットワークのモデルとその進化についてお話しします。
ポスター
第13回
詳細
2020.1.24
測るを極める
― 細胞内に迫る生体分子質量分析イメージング ―
●兼松 泰男(基礎理学プロジェクト研究センター)
生体分子の分布を直接観察する、質量分析イメージング。この極限性能に迫り、細胞内の分子イメージを捉える研究を紹介します。イオン光学、レーザー光学など、技術の高度化について触れ、原理から理解し開発・活用する装置開発型実験研究についてお話します。
ポスター
第14回
詳細
2020.1.31
分子性電気伝導体と巨大応答現象
●花咲 徳亮(物理学専攻)
世の中には、プラスチック等のように炭素で作られた分子性(有機)物質が満ちあれています。これらは、電気を流さない物だと、昔は思われていました。ところが、分子から電子を少し引き抜いたり加えたりすると、分子性物質が電気を流す金属になることが知られてきました。この分子で作られた金属は一方向しか電気を流さないなど、銅などの一般的な金属とは異なるユニークな性質を持っています。
私達は、分子に金属的な性質だけではなく、磁気的な性質をも付与した物質を研究しています。このような分子性物質に磁場をかけると、電気抵抗が大きく変化する巨大磁気抵抗効果が見出されました。巨大磁気抵抗効果は、 ハードディスクの磁気検出素子としても利用されている有益な現象です。本談話会では、分子性物質を手始めに強相関電子系における巨大応答現象の話を、わかりやすく紹介したいと思います。
ポスター
輪講世話人
●横田 勝一郎 F421, yokota あっと ess どっと sci.osaka-u.ac.jp
●(TA) 平井 隼人、久保田 充紀