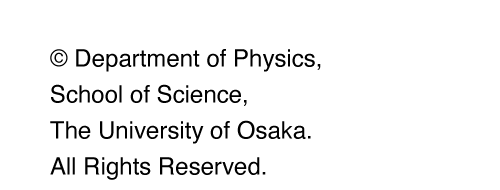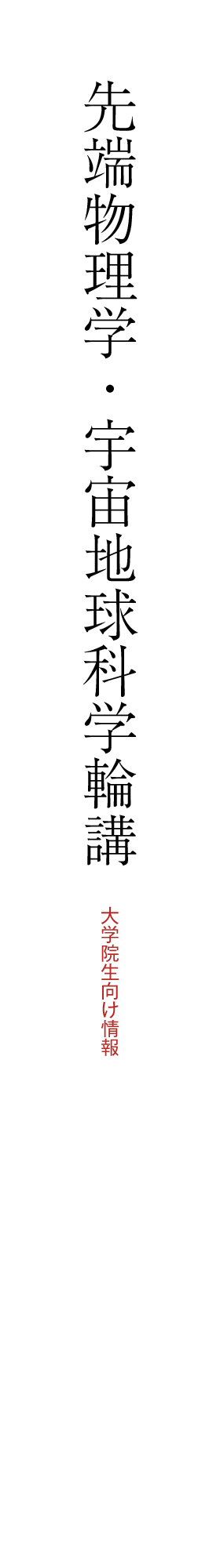
2018(H30)年度
先端物理学・宇宙地球科学輪講
●日時
秋・冬学期 金曜日4時限(14:40〜16:10)
●場所
理学部D501大講義室
●出席・レポート
毎回、授業中にミニレポートを書いて提出してください。
講義日程
第1回
2018.10.5
ガイダンス
●大高 理(宇宙地球科学専攻)・酒井 英明(物理学専攻)
第2回
詳細
2018.10.12
系外惑星と地球外生命探査
●住 貴宏(宇宙地球科学専攻)
太陽以外の星の周りを回る惑星:系外惑星は、既に3千個以上見つかっている。これらがどの様に発見されてきたか、また、今後の地球外生命探査について紹介する。
ポスター
第3回
詳細
2018.10.19
素粒子物理学の謎ー実験によるアプローチー
●南條 創(物理学専攻)
素粒子物理学は目覚しい発展を遂げてきた。これまでに何が分かって、どんな謎が残され、それに対してどのような実験的アプローチをしているのかを解説する。欧州の最高エネルギー加速器を用いるATLAS実験と、国内で進行中の大強度加速器を用いるKOTO実験という2つの実験を具体例に挙げる。
ポスター
第4回
詳細
2018.10.26
仲の悪い電子たちと仲のよい電子たち
~超伝導の起源~
●黒木 和彦(物理学専攻)
超伝導は、電気抵抗の消失という劇的な現象によって多くの研究者を魅了する。1986年に発見された銅酸化物高温超伝導は、それまで20K台であった転移温度の世界記録を一気に130K超にまで引き上げた、一大ブレークスルーであった。さらに2008年には鉄ヒ素系化合物において50Kを超える新たな高温超伝導体が発見され、大きな関心を集めてきた。
本輪講では、超伝導の起源に焦点をあて、従来型の超伝導と高温超伝導体の共通点と相違点を論じて、後者の面白さを伝えたい。
ポスター
第5回
詳細
2018.11.9
統計物理モデルで見る地震
●川村 光(宇宙地球科学専攻)
地震は、地殻の弱面たる地震断層がプレート運動によって駆動されて示す、大規模な固着すべり摩擦不安定性である。統計物理的なモデルに基づいて、地震現象の物理的な本性を探るアプローチについて紹介したい。
ポスター
第6回
詳細
2018.11.16
強磁場の世界
●萩原 政幸(先端強磁場科学研究センター)
子供の頃、砂鉄を用いて馬蹄形磁石や棒磁石の周りに模様ができて不思議だなと思った人もいることでしょう。宇宙にはとてつもなく強い磁場が存在し、我々の体を作っている分子がばらばらになる磁場や粒子-反粒子の数を変えてしまうほど強い磁場が存在すると考えられています。今年度は1000テスラを超える屋内最高磁場の発生という特筆する出来事が日本でありました。我々のセンターは、国内最大の蓄電エネルギーを持つコンデンサーを有しています。講義の後半はこれを用いて発生させた強磁場下でどのような研究を行っているのかを、阪大強磁場施設の歴史と共に紹介します。
ポスター
第7回
詳細
2018.11.30
高強度レーザーによる宇宙物理学実験
ー 高エネルギー天体現象のシミュレーション ー
●中井 光男(レーザー科学研究所)
宇宙物理学では、宇宙の諸現象を地上で検証された物理によって理解しようとします。しかし、多くの宇宙・天体現象は、従来地上では実現できなかった極めてエネルギー密度の高い環境で実現される、非平衡・多階層の複雑系を形成しています。そのため、理論や計算機シミュレーションの妥当性を検証するためには、特徴的な現象を抽出した模擬実験が不可欠です。
近年、高出力・高強度レーザーの出現によって、超新星爆発に代表される爆発現象、無衝突衝撃波による宇宙線加速や磁場生成・増幅、磁気リコネクションによる相対論的粒子加速、相対論的プラズマや電子・陽電子プラズマの生成、高輝度γ線核合成など、未踏の「高エネルギー密度状態」下での宇宙現象の模擬実験が可能となりました。本輪講では、最近の具体的な実験例を紹介しながら、この分野での先駆的な論文[1]を解説します。
[1]H. Takabe, Progress oh Theoretical Physics Suppl. 143, 202-265(2001),
https://doi.org/10.1143/PTPS.143.202.
ポスター
第8回
詳細
2018.12.7
重力波を通じて宇宙を探検する
Exploring the Universe through gravitational waves
●Luca BAIOTTI(宇宙地球科学専攻)
アインシュタインによる重力波予測の100年後に当たる2015年にようやく重力波の検出に成功した。アインシュタインの理論(一般相対性理論)によると、重力は時空の曲率の現れであり、物質は時空の曲がり方を決定する。
したがって、天体などが動くと、時空間の曲率が変化する。この変化が波のように伝播する現象は重力波と呼ばれている。重力波を観測することで、連星ブラックホールの合体や連星中性子星の合体、超新星爆発、ビッグバンなど、宇宙に関する基本的な新しい情報を得ることができる。本講義では、数値相対論によるシミュレーション結果なども含めたフロンティア研究について紹介する。
100 years after Einstein's prediction of gravitational waves, they have
finally been detected, in 2015. According to Einstein's theory of
general relativity, gravity is a manifestation of the curvature of
spacetime and matter determines how spacetime is curved. Therefore, when
matter moves, spacetime curvature changes and when these changes
propagate like waves, they are called gravitational waves. By observing
gravitational waves, we can get fundamentally new information on
astrophysical and cosmological events, like black-hole mergers,
neutron-star mergers, supernova explosions, big bang and much more.
In this lecture, I will show some of the results from frontier research
including numerical-relativity simulations.
ポスター
第9回
詳細
2018.12.14
ブラックホールと量子力学
●飯塚 則裕(物理学専攻)
アインシュタインは、今からほぼ100年前に、「物理は、座標系という人間が勝手に時空に手でつけた目盛などに依存するはずがない」という原理(一般相対性原理)と、「慣性力と重力はそもそも区別できないはずだ」(等価原理)という二つの原理から、一般相対論をほぼたった一人でつくりあげました。この非常に美しい理論は100年たった今でも人々を魅了し、多くの研究がなされています。
本講演では先人たちによる非常に賢い「思考実験」を通じて、
一般相対論が予言する「ブラックホール」という、光さえもその強力な重力によって脱出できない物体に、現代物理学のもう一つの柱である量子力学の理論を適用すると、どのように不思議な現象がおこるのか、またそれがいかに「量子重力理論」、「弦(ひも)理論」の鍵や試金石となるのかについて紹介したいと思います。
ポスター
第10回
詳細
2018.12.21
エンタングルする宇宙と精密観測
●菅野 優美(物理学専攻)
最近、私たちの宇宙は因果的に離れた多くの宇宙の中の1つにすぎず、宇宙初期には他の宇宙と互いに量子論的にエンタングルしていたことが、ストリング理論によって示唆されています。また、初期宇宙の理論であるインフレーション理論は、宇宙の構造や宇宙背景放射の温度揺らぎを、量子揺らぎから説明することに成功しました。この講義では、初期の宇宙が本当に量子揺らぎから始まったのか、その際他の宇宙とエンタングルしていたのか、その痕跡を宇宙背景放射から探ります。
ポスター
第11回
詳細
2019.1.4
光子から電子スピンへの量子状態変換と量子情報処理への展開
●大岩 顕(産業科学研究所)
近年、量子情報処理への応用を出口に、固体中の量子状態の精密な制御や検出が可能になり、固体物理の基礎学理としても新しい可能性が広がりつつあります。今回は、半導体量子ドットを使い、光子と電子スピンという異種量子状態間での量子状態の変換や、光子対から電子スピン対へのもつれ変換などの最近実験と、量子情報処理への応用を紹介します。
ポスター
第12回
詳細
2019.1.11
物理と化学を駆使して地震を理解する
-来たる南海トラフ地震に向けて-
●廣野 哲朗(宇宙地球科学専攻)
昨年は大阪府北部地震が発生し、本学も大きな被害を受けました。さらに、関西は数10年後に必ず発生する南海トラフ地震を控えています。自宅でできる地震への備えは言うまでも無く必要ですが、理学部で学んだ物理・化学を如何に駆使して、地震理解にチャレンジしているのか、その最先端を紹介します。
ポスター
第13回
詳細
2019.1.25
界面の物理学-物質の可能性を追求する-
●松野 丈夫(物理学専攻)
我々の身近にある物質の多様な性質(物性)は、電子という一種類の素粒子により実現しています。すなわち、物質はマクロな物性とミクロな電子を結ぶ舞台であり、物理学の魅力的な対象です。その中でも、二つの異なる物質が接する境界=界面は、単一の物質では実現できない豊かな物性の舞台となっています。原子レベルで制御された界面で電子のふるまいを調べることで、物理学の新たな世界が見えてきます。界面の物理学を通して、物質が持つ大きな可能性についてお話しします。
ポスター
第14回
詳細
2019.2.1
原子核のクラスター相関と宇宙における元素合成
●川畑 貴裕(物理学専攻)
原子核の内部では陽子と中性子が比較的自由に運動していると考えられていますが、時として、複数の陽子と中性子が強く結びついてクラスター構造を持つことが知られています。この「クラスター相関」を調べる研究についてお話します。
また、現在の宇宙に存在する全ての元素は、138億年におよぶ宇宙進化の過程において原子核反応によって生成されたと考えられています。この原子核反応にもクラスター相関は重要な役割を果たしています。「クラスター相関」をキーワードに宇宙における元素合成過程を調べる研究についても紹介します。
ポスター
輪講世話人
●大高 理 F326, ohtaka あっと ess どっと sci.osaka-u.ac.jp
●(TA) 平井 隼人